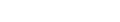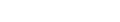公開日:2025年8月18日
退職金の資産運用はどうする?初心者でも安心の始め方と一時払い終身保険の活用方法
退職金は、老後のための大切な資金です。その使い道は人それぞれですが、長寿化とともに長くなる老後の生活を安心して過ごすために「資産運用」を検討する人も少なくありません。ただし、老後の大切な資金であるからこそ、押さえておきたい基本や注意が必要なポイントもあります。この記事では、退職金の運用について、基本からよくある悩み、初心者でも始めやすい運用方法までやさしく解説します。
目次
運用にはリスクも伴うため、むやみに始めるのではなく、基本的な知識を押さえておく必要があります。まずは退職金を運用する前に知っておきたい3つの基本について確認してみましょう。
退職金運用は「目的」と「期間」で決まる
退職金を運用する際は、老後資金を「使う予定」と「増やしたい金額」の2つの視点で考えてみるとよいでしょう。「使う予定」に関しては、支出の目的に応じて次の3つに分類できます。日々の暮らしに必要な「生活資金」、いつ発生するかわからない「医療・介護費」、そして突発的な支出や余暇のレジャーにも使える「ゆとり資金」です。それぞれについて、必要な期間や準備しておきたい金額を見積もりましょう。
もし、その金額をすでに確保できているのであれば、無理に高い利回りの運用を目指す必要はなく、定期預金など堅実な運用が適しているかもしれません。
一方、将来に備えて資金を少しでも増やしながら取り崩していきたい場合は、「いくら増やしたいのか」「そのためにどれくらいの利回りが必要か」を踏まえたうえで、目的に合った運用方法を検討しましょう。
退職金を運用するにあたってやってはいけないこと
退職金は、老後の生活を支える大切な資金です。だからこそ、運用にあたっては慎重な判断が必要です。ここでは、特に注意しておきたい「やってはいけないこと」を3つご紹介します。
1つ目は、広告や勧められるままに運用商品を購入することです。「最近この商品が人気」、「この商品で大きく儲けた人がいる」などと聞くと、つい買いたくなってしまいますが、その商品内容をしっかり確認し、自分の目的に合っているかどうかをよく確認して選ぶようにしましょう。
2つ目は、短期的な利益を狙って無計画に投資することです。退職金は一発逆転を狙う資金ではありません。リスクが大きい商品に集中投資をしたり、相場の上下に一喜一憂して投資を繰り返すと、資産を大きく減らしてしまう可能性があります。
3つ目は、「元本保証=安全」と思い込むことです。元本保証の商品であっても、インフレ(物価上昇)で実質的な価値が目減りする可能性があり、完全に安全とは言えません。リスクの種類を正しく理解しておくことが重要です。
自分に合った退職金運用スタイルを見つけよう
退職金を上手に運用するためには、まず「自分に合った運用スタイル」を見つけることが何より大切です。資産運用に正解はありません。大切なのは自分に合った運用方法を選ぶことです。
最初に考えたいのは「リスク許容度」です。値動きのある商品で一時的に資産が減ったとき、どの程度まで冷静でいられるかは人それぞれです。年齢、収入、家計状況なども踏まえて、「どの程度のリスクなら受け入れられるか」を、各商品詳細をみて自己診断してみましょう。
次に、投資経験や金融知識レベルも重要な判断材料になります。初心者であれば、まずは比較的リスクが低く、仕組みがわかりやすい商品から始めるのが安心です。逆に、ある程度投資経験があるなら、自分のスタイルに応じて幅広い選択肢が検討できます。
無理せず、自分に合った運用スタイルを見つけることが、退職金運用への第一歩です。
次に退職金の運用で多くの人が直面する悩みとその解決策を紹介します。
「退職金が減るのが怖い」→リスクコントロールの工夫
退職金を運用する際、特に投資経験が浅い人は「資産が減るのが怖い」と感じるのはごく自然なことです。その場合は、元本保証の商品と値動きのある商品をバランスよく組み合わせることで、リスクを調整することができます。
例えば、定期預金や個人向け国債といった安定した方法で資産を一定割合保有しつつ、残りを投資信託などで運用する方法が考えられます。
さらに、定期的に資産の配分を見直し、相場環境やライフステージの変化に応じて運用比率を調整することで、リスクをコントロールしながら安定した運用が目指せます。
「専門用語が難しい」→シンプルな商品を選択する
運用を始めようと商品について調べると、「専門用語が多くてよくわからない」と感じる人も少なくありません。
そのようなときは、急に複雑な仕組みの商品や、リスクがわかりにくいもの、意味を正しく理解できない商品から始めるより、まず、様々な情報源から知識を習得していく習慣をつけましょう。
そして、まずは自分が仕組みを理解できる範囲で、比較的シンプルな商品から運用を始めるのが安心でしょう。知識や経験が増えれば、徐々に運用商品の選択肢も広がっていきます。
「家族に相談しづらい」→情報共有のタイミングと方法
退職金の使い道や運用について、家族に話しづらいと感じる人も多いようです。
しかし、いざというときに家族が何も知らない状態では、資産の管理や引き継ぎがスムーズにいかないおそれがあります。無理にすべてを共有する必要はありませんが、どのような資産をどこに預けているか、誰にどの情報を伝えるか、そしてそのタイミングを事前に考えておくことが大切です。
例えば、年に一度、簡単なメモや資産の一覧を共有する機会を設けるなど、自分に合った形で情報を少しずつ伝える工夫をしてみましょう。
また、将来高齢になったときに判断力が低下する可能性も考慮し、信頼できる相談相手を見つけておくことも大切です。家族だけに限らず、第三者(友人、専門家、地域の支援者など)も含めて検討してみましょう。成年後見制度についても調べておくとよいかもしれません。
退職金は一度きりの大きな資金ですが、使い方次第で将来の安心感が大きく変わります。貯めるだけでなく、無理のない範囲で資産運用を活用することで、老後をより安心して暮らせる備えになります。
「もらって終わり」じゃない退職金の活かし方
退職金は「もらって終わり」ではなく、これからの長い人生を支える大切な資金です。公的年金に上乗せしたい生活費や、医療・介護といった予期せぬ出費、さらにはインフレによる物価上昇への備えも必要です。
平均寿命が延びる中、老後の生活が30年以上続くことも珍しくありません。そのためには、退職金を計画的に使いながら、一部を運用して将来に備えることが安心につながります。
長寿時代を安心して暮らすためには、退職金をどう守り、どう活かすかが重要なカギとなります。
初心者でも取り組みやすい資産運用の選択肢
退職後の資産運用は、「守りながら増やす」ことが大切です。
例えば一時払い終身保険は、一度の保険料払い込みで一生涯の死亡保障を得られるだけでなく、資産形成や相続対策としても有効です。
また、公社債やバランス型の投資信託を活用すれば、比較的リスクを抑えながら安定的な運用が期待できます。
さらに、NISA制度を利用すれば、運用益に対する税負担を軽減し、効率よく資産を増やすことが可能です。特に運用が初めての方は無理なく始めやすい方法を選ぶようにしましょう。
※ NISAはマニュライフ生命では取り扱っておりません。
退職金を運用しながら、家族への保障や相続への備えもしたい。そんな方に注目されているのが「一時払い終身保険」です。退職金運用に一時払い終身保険を活用するポイントについて見てみましょう。
一時払い終身保険について
一時払い終身保険とは、保険料を一度にまとめて払い込むことで、一生涯にわたる死亡保障を受けられる生命保険です。契約後すぐに保障が開始され、万が一のときに受取人が相続人であれば非課税枠が適用されるため、老後資金の保全や相続対策として広く活用されています。
「円建て一時払い終身保険」のほかに、米ドルなどの外貨で運用を行う「外貨建て一時払い終身保険」、株式や債券などを投資対象とする特別勘定で運用する「一時払い変額終身保険」などがあります。それぞれ運用の方法やリスク・リターンが異なるので、仕組みをよく理解することが大切です。
・円建て一時払い終身保険
円建て一時払い終身保険とは、日本円で保険料を契約時に一括で払い込む終身保険です。
そして日本円で運用し、死亡保険金も日本円で受け取ります。
円建て一時払い終身保険には、前述で紹介したようなメリット・デメリットがあり、相続などにも活用できます。
・外貨建て一時払い終身保険
外貨建て一時払い終身保険とは、契約時に保険料(円または外貨)を一括で払い込み、その後は米ドルなどの外貨で運用を行う保険です。保険金などを受け取る際は、円で受け取ることもできますし、外貨での受け取りを可能としている商品もあります。
外貨で運用する以上、為替の影響を受けるため、死亡時に受け取る円換算の死亡保険金額は、その時の為替レートなどによって、払い込んだ時の円換算の保険料総額を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあることに注意が必要です。
また、外貨建ての一時払いには、諸費用がかかります。保険契約の締結・維持などに必要となる保険契約関係費、解約時に発生する解約控除などがあり、商品によっても異なるため契約時には必ず契約締結前交付書面などで確認しましょう。
・一時払い変額終身保険
一時払い変額終身保険とは、契約時に保険料を一括で払い込み、その後は株式や債券などを投資対象とする特別勘定(ファンド)といわれる運用先を自分で選択し、運用しながら万一の際の保障を準備する商品です。特別勘定の運用実績によって保険金額や解約返戻金などが変動する点が特徴です。そのため、解約返戻金額などは払い込んだ保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあることに注意が必要です。
特別勘定の内容は保険会社によって異なりますが、多くの場合複数用意されており、自分で好きな特別勘定を選ぶことができます。選ぶ特定勘定は1つだけでなく、複数を組み合わせての運用が可能な商品もあります。
投資対象とする投資信託などはリスクやリターンが異なります。 なお、リターンとはその運用商品から得られる運用成果のことで、リスクとはその運用商品の不確実性、つまり値動きの幅のことです。
リスクとリターンは正比例の関係にあり、リスクが低い運用商品はリターンが少なく、逆にリターンが多い商品はリスクも高くなります。
そして、一時払い変額終身保険にも、諸費用がかかります。保険契約の締結・維持などに必要となる保険契約関係費、特別勘定の運用により発生する資産運用関係費、解約時に発生する解約控除などがあり、商品によっても異なるため契約時には必ず契約締結前交付書面などで確認しましょう。
退職金の使い道として一時払い終身保険が向いている理由
退職金の使い道として一時払い終身保険が選ばれる理由は、万一の死亡や高度障害の保障と相続対策の両方を実現できる点にあります。
保険料を一括で払い込むことで、契約後すぐに一生涯の保障が得られ、万が一の際に、ご家族に安心を残せるのが魅力です。
また、保険商品によっては、特定疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態になった場合の保障があったり、死亡のみでなく病気になった場合にも備えられるものもあります。
ただし多くの保険会社は、がんの保障には90日間の保障されない期間(不てん補期間、待機期間)があるため、加入後すぐに保障が開始しない点に注意が必要です。
賢く活用するポイントをご紹介
一時払い終身保険を賢く活用するには、複数の保険会社や商品の特徴を比較検討することが重要です。商品によって、仕組みや保障もさまざまのため、自身にあったものを選びましょう。
注意したい点は、一時払い終身保険は一生涯・長期で続けるもののため、やむを得ない事情で短期間で解約する場合には、元本割れとなる可能性もあります。
仕組みは保険商品によって異なりますので、パンフレットや設計書などで事前に確認をしましょう。
また、外貨建てや変額型の商品は為替リスクや運用リスクを伴うため、自身のリスク許容度をしっかり見極めたうえで選びましょう。相続対策と一体的にプランを立てることで、退職金をより効果的に活用できます。
退職金の運用は、老後の安心を左右する重要な選択です。ただし、ライフスタイルも必要な金額も人それぞれ。したがって、どのような運用スタイルが合っているかも人によって千差万別です。
本記事で紹介した退職金運用のポイントや考え方も参考にしながら、焦らず、自分に合った運用スタイルを見つけてみてください。それが退職後の生活をより豊かにする第一歩です。
長尾 真一
ファイナンシャルプランナー(AFP認定者)、企業年金管理士(確定拠出年金)
1977年広島県生まれ。大学卒業後、医療機器メーカー・エアライン系商社で海外営業として勤務した後、ファイナンシャルプランナーに転身。生活に関わるお金の不安を解消し、未来に希望をもって暮らしていくためのお手伝いをする「生活設計のコンシェルジュ」として相談業務や執筆業務に従事。企業や学校での講演・セミナーにも年間100回以上登壇しており、これまでの延べ聴講者数は2万人を超え、わかりやすい説明が好評を得ている。
※記載内容および税務上のお取り扱いについては、2025年6月現在の内容であり、今後、税制の変更などによりお取り扱いが変更となる場合がありますのでご注意ください。また、個別の税務などの詳細については税務署や税理士など、専門家にご確認ください。
※このコラムの内容は各商品・制度の情報提供を目的としたものです。一般的な説明であり、特定の商品を説明・推奨・勧誘するものではありません。取扱会社などによって、お取り扱いが異なる場合がありますので、各資料などをご確認いただき、ご意向に沿ったものをご検討ください。
MLJ(CMD) 25070513